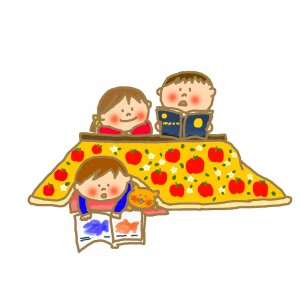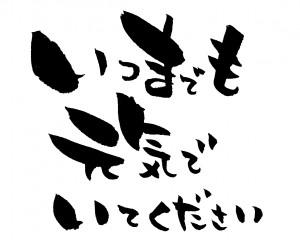自分自身の親や近親者が亡くなってしまう年齢になりました。
喪中を迎えると、一般的にはお祝い事を控える、
年賀状を出さないことやお正月の飾り一式をやらないことなどなんとなくわかることもあります。
おじいさんやおばあさんが亡くなった時は、子供だったのでそんなこと気にしていなかったのですが、
大人になり、家族も持てば喪中についてもきちんとしないといけないと考えるようになりました。
喪中で年末年始を迎えるにあたり、
喪中のお正月はどう過ごしたらいいのか、
初詣や門松、鏡餅などはやっていいのか、
と思われることはないでしょうか?
最近は喪中に対しての意味も薄らいで来てはいますが、喪中のお正月の過ごし方を紹介したいと思います。
喪中の意味や期間は?
●喪中は、亡くなった親や身近な人に対して冥福を祈り、
一定期間の間は普通の生活状況ではなく、お祝い事や派手な行動を自粛している状態のこと。
亡くなった人への悲しみが深いので、
お祝い事などの楽しいことをしたくない、
亡くなった人に申し訳なくてしてはいけない
と自然と感じてしまうのではないでしょうか。
●喪中の期間は、「忌」と「服」の期間に分かれています。
自分の親や子供、配偶者の場合は、「忌」の期間が最長50日間。
「服」の期間が最長13か月というのが一般的です。
この二つの期間を合わせたものが喪中とされています。
喪中のお正月の過ごし方は?
①喪中であっても、お祝い事を家族や身内や親しい人の内輪内であれば行うこともあります。
ただ、対外的には喪中なので表沙汰になることは控えます。
詳しく言えば、
【家の中で行うこと】
・おせち料理を食べる
・お雑煮を食べる
・お年玉をあげること
・年越しそばを食べること
こういうことは喪中でもやっても構いませんね。
家の中での、「家族全員の健康や幸福を願うこと」
「その一年の無事を祈ること」はむしろやったほうが良いでしょう。
【控えること】
・年賀状を出すこと
・門松やしめ縄、鏡餅などのお正月のお飾り
・神社への初詣
・年始回りなどはしない
一般的には非常識になってしまうため、控えたほうが良いです。
初詣については、神社では基本的に忌の期間が過ぎていれば、
お参りして構いません。忌の期間は控えましょう。
②喪中にやってはいけないことすべてを明確に決められているわけではないです。
気持ちの部分で亡くなった人偲んで、お正月の飾りをしたり、初詣に行ったりと
おめでとうという気持ちになれないのなら、お正月の行事を自粛してしまうのが良いでしょう。
逆に亡くなった人への気持ちの切り替えができ、悲しみからも気持ちの切り替えができて、
お祝い事に参加したい、神社で初詣したいと考えるのならもう喪中ではないと思います。
お正月の過ごし方は、自ずと気持ちが決めてくれるでしょう。
まとめ
喪中の風習は残っていますが、昔ほど強く縛られるものではないと思います。
一番大事なのは気持ちの問題です。
故人を思う気持ちが強いほど、喪中の間のお祝い事は控える気持ちが出てきますし、
慎んで毎日を過ごそうってなると思います。
お正月の過ごし方でも、自分の気持ちによるところが大きいですね。
毎年、家族全員が無事に一年を過ごして、お正月を迎えればいいですね。
合わせて読みたい!⇒新年の挨拶を喪中の人とメールでする場合どうすればいいの?